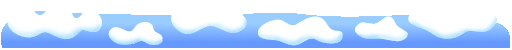
観光スポット:往生院
| 行基の師・道昭が白鳳8年(680)に建立した名刹で、境内には珍しい二面石仏がある。左右両面に仏が刻まれた長方形の石碑であり、道昭の建立を確認した鎌倉時代の石仏と言われる。 当時は信達(しんだち)地区を寺領として五丁四方を有し、飛鳥様式の伽藍が整然と並んでいたといわれる。 信長の根来攻めで堂塔が焼失した。文禄年間の太閤検地で404坪と狭くなり、明治には293坪までに狭くなった。京都の仁和寺に属する真言宗の寺である。 道昭は、海運・造船・土木に長じた部族の一員だった。長安に留学し玄奘三蔵に学んだという。奈良の元興寺に住んでいたときに法相宗を開祖した。 往生院へのアクセスは、ここをクリックして地図をご覧ください。 |
コース一覧へ


